 コタロー
コタローこんにちは!コタローです。
(@kotaro_kaigo_v)
サービス提供責任者は、デスクワークや現場仕事など多岐にわたる仕事をおこないます。
役職に「責任者」という名称がある通り現場から事業運営の一端を担う重要なポジションです。
今回は、私が働いている訪問介護のサービス提供責任者の仕事内容と1日の流れを紹介させていただきます。
- サービス提供責任者を目指している方
- サービス提供責任者として働いている方
- 訪問介護の仕事に興味がある方
【訪問介護】サービス提供責任者とは?

 コタロー
コタロー「サービス提供責任者」という仕事をご存知ですか?
現場ではサ責とかサー責、一番短いとSとかって略されて呼ばれています。Sと略されるのはレアです…
サービス提供責任者とは、訪問介護におけるサービスの調整や援助を受ける方への契約、ヘルパーさんの指導・育成などが主なお仕事になります。
サービスのコーディネート、ヘルパーさんへの仕事依頼・資質向上における研修の実施など多岐に渡ります。全体的な調整役ですね。
訪問介護において、サービス提供責任者になるためには、いくつかの要件があります
- 実務者研修修了
- 介護福祉士
- 看護師、准看護師、保健師
- ヘルパー1級、介護職員基礎研修修了(旧)
以上の資格をお持ちの方はサービス提供責任者になれます。
しかし、「4」のヘルパー1級・介護職員基礎研修はすでに廃止された資格なので、取得されている方のみが対象です。2022年現在ですと最短は実務者研修修了の資格になります。
では、次の項目ではどのような仕事・業務をしているかをご説明させていただきます。
サービス提供責任者が行なうべき主な業務内容

サービス提供責任者が行なう主な業務は、1〜6までの内容になります。
色々と範囲が広いので覚えるのが大変ですが、一貫性がある内容なので覚えやすいかと思います。
ヘルパーの指導・育成、業務管理
名称に責任者という肩書きがあるので、基本的にヘルパーへの指導・育成は重要な任務です。
はじめて現場に出るヘルパーだけでなく、在籍しているヘルパーに対しても介護技術や新規のご利用者様に対する援助の方法を指導します。
また、介護技術の向上等を考え研修も定期的に実施します。
各ヘルパーにより得て不得手があることや、訪問する家によっては犬や猫などのペットを飼われていることもありますので、アレルギーがある等その聞き取りも行いシフトの調整も行ないます。
ご利用者様の状態・意向の把握
体調や環境の変化もそうですが、在宅生活上でどのように過ごしたいかを面談にて聞き取りを行います。また、ご本人のみならず介護を行なっているご家族面談も行い意向を聞き取りします。
新規ご利用者様のサービス調整に係る業務
新しくサービスの依頼があった場合のヘルパーの手配やアセスメントを行います。
どのようなサービスが必要なのかを判断するため、困りごと・体調・生活環境の確認を行なうとともに必要なサービスの提案や契約業務を行います。
アセスメント(課題分析)、契約は重要な業務でありサービス開始前には必ず確認を取りましょう。
具体的な援助目標・援助内容の指示とご利用者様の状況についての情報共有
実際にサービスが始まったら、日常生活上で問題があった場合や体調変化時などは、サービスに関わっているヘルパーや他職種の方々と情報共有をし連携を図ります。
訪問介護や施設介護もそうですが、チームケアを優先させる必要があります。
訪問介護計画書の作成
ケアマネジャーが立てた支援計画(ケアプラン)に沿い、訪問介護が係わる面でどのような目標を立て支援をしていくかを記した訪問介護計画書を作成します。
簡単にいうと、どのように支援をしていき希望の目標を達成できるかを考えた計画書です。
- どのように困りごとが解消できるか
- 安心した在宅生活を送れるか
- どんな成果を得られるか
訪問介護計画書を作成するときは、目標を立てます。
目標はとても重要でその方の行動指針にもなりますので目標を立てる際は、達成が可能か、ご本人もその目標に同意をしているのか、達成までの目標を低いものから設定し成功体験を積めるか等を考慮し作成していきます。
モニタリングの実施
モニタリングは、訪問介護計画書で立てられたサービスが実情に合っているか、利用者様の心身状況や生活環境などを加味し月に1回程度評価を行います。
訪問介護の援助は毎日、高頻度で利用者様に係わるため、小さな変化なども見つけやすい立場です。
そのため、変化があればケアマネジャーや他職種との連携を図りサービス内容の見直しなども必要になってきます。
現場に出て援助をしたり、書類作成やヘルパーさんの指導育成大切な仕事です。そのためスケジュール管理も大変で計画的に業務を進めていける工夫が必要です。
私は、手帳を使用してスケジュール管理を行っており、1ヶ月の行動予定を把握して業務を円滑に進めることができています。
サービス提供責任者の1日の流れ

 コタロー
コタローサービス提供責任者のある1日の流れを見ていただきたいと思います。
パターン1
| 9:00 | 出勤・朝礼 |
| 9:30-10:00 | 【1件目】排泄、更衣、服薬介助 |
| 10:30-11:30 | 【2件目】掃除、買い物代行 |
| 12:00-13:00 | 昼休憩 |
| 13:00-15:00 | 事務作業、連絡調整など |
| 15:30-16:30 | 【3件目】入浴介助、水分補給 |
| 17:00-18:00 | 事務作業、翌日の準備、退勤 |
いい流れですね。これだと事務作業や調整業務もはかどります。
パターン2
| 8:30-9:00 | 【1件目】排泄・更衣介助、清拭 |
| 9:30-10:00 | 【2件目】透析の送り出し準備、排泄、更衣、移乗介助 |
| 10:30-12:00 | 【3件目】買物同行、調理、後片付け |
| 12:30-13:30 | 【4件目】排泄、食事、服薬介助 |
| 14:00-15:00 | 昼休憩 |
| 15:15-15:45 | 【5件目】透析帰宅後の排泄、更衣、移乗介助 |
| 16:15-16:45 | 【6件目】デイサービス帰宅後の排泄、更衣、移乗介助 |
| 17:00-18:00 | 【7件目】排泄、更衣介、食事介助 |
| 18:30- | 翌日の準備、必要事項の連絡と利用者様のサービス調整業務など |
きつい流れですね…
ヘルパーさんのお休みなどが重なった場合や急な依頼が入ったときはこのような流れになります。
2パターンを例に挙げさせていただきましたが、サービス提供責任者といえども現場業務との兼務があります。
1日事業所にいる日は少ないです(サービス提供責任者は現場にほとんど出ない職場もありますので、一概には言えませんが…)。
例に挙げたパターン2のような流れはよくあります。
中には1日9件の訪問を8時間の勤務内で稼働することもあります。この場合であると事務所に戻り事務作業などは確実にできません…
上記の項目で「行なうべき業務」とありますが、行なうことがままならない状態に陥ってしまうこともあります。
そうならないためには、計画的に業務をこなすことが求められます。
介護保険を利用しての公的サービスであるため、書類、人員体制などについては適切にご利用者様に対して援助が行えているかの確認のため一定期間ごとに「運営指導」というものがあります。
運営指導での指摘事項が悪質なものであれば監査へ移行し、今まで受け取った報酬の返還もありますので、書類作成などは確実に行わなければなりません。
おわりに

色々とお話させていただきましたが、内容的には結構大変だなぁ…と思われた方やそんなもんか。と思われる方もいらっしゃると思います。
私が今現在もまだ訪問介護の業務についているのは、やはり「やりがい」があることと、ご利用者様が自宅で「自分らしく生活を送れる」環境を作るお手伝いができることに魅力を感じています。
あとは、外回りが多いので結構気が楽だったりもします。
または、四季の移り変わりを楽しんだりと色々とサボりも入れながら楽しんで仕事しています。
もうひとつ大事にしていることはサービスを提供する際は、自分が受けるんだったらこんなサービスを受けたいな!とか考えながらサービス提供を行なっております。
訪問介護だけにかかわらず、介護業界自体が人材確保が難しい状態です。
理由として、介護は給与が低い・キツイ・汚いなどのいわゆる3kなども以前はよく聞いていましたね。
現在はコロナウイルスの影響で感染の恐怖にさらされている状況でもあり、敬遠されがちなのとコロナを理由に退職をされてしまう方もいます。
しかし、現在は介護職員の処遇改善と言う名目の加算なども増設されてきており、給与アップもしてきております。
また、残業代もしっかりと出るところはでます。
コロナに関しては、適切な対処の研修も実施し「感染予防に努めております。介護に興味がない方でもまずはアルバイトからでも介護の業界にかかわってみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


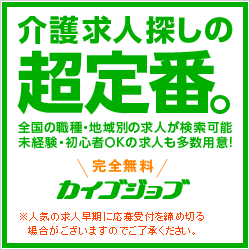









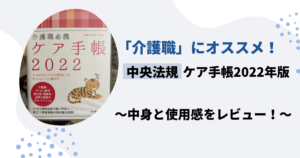
コメント